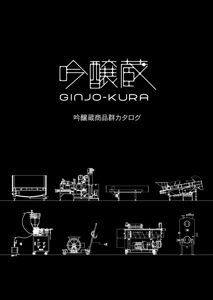- 公式HPリンク
- トータルエンジニアリング
- SAKE Brewery Interview (酒蔵記事)
- 記事制作について
- The Art of Sake Brewing 1
- The Art of Sake Brewing 1(ENG)
- The Art of Sake Brewing 2
- The Art of Sake Brewing 2(ENG)
- The Art of Sake Brewing 3
- The Art of Sake Brewing 3(ENG)
- The Art of Sake Brewing 4
- The Art of Sake Brewing 4(ENG)
- The Art of Sake Brewing 5
- The Art of Sake Brewing 5(ENG)
- The Art of Sake Brewing 6
- The Art of Sake Brewing 6 (ENG)
- The Art of Sake Brewing 7
- The Art of Sake Brewing 7 (ENG)
- 設備デザイン
- 展示会・セミナー
- FTIC(未来技術革新委員会)
- 補助金サポート
- 生産性向上要件証明書
- 微生物インダストリープラットフォーム
- Enz Koji
- 一般食品
- お問い合わせ
The Art of Sake Brewing (vol.6)
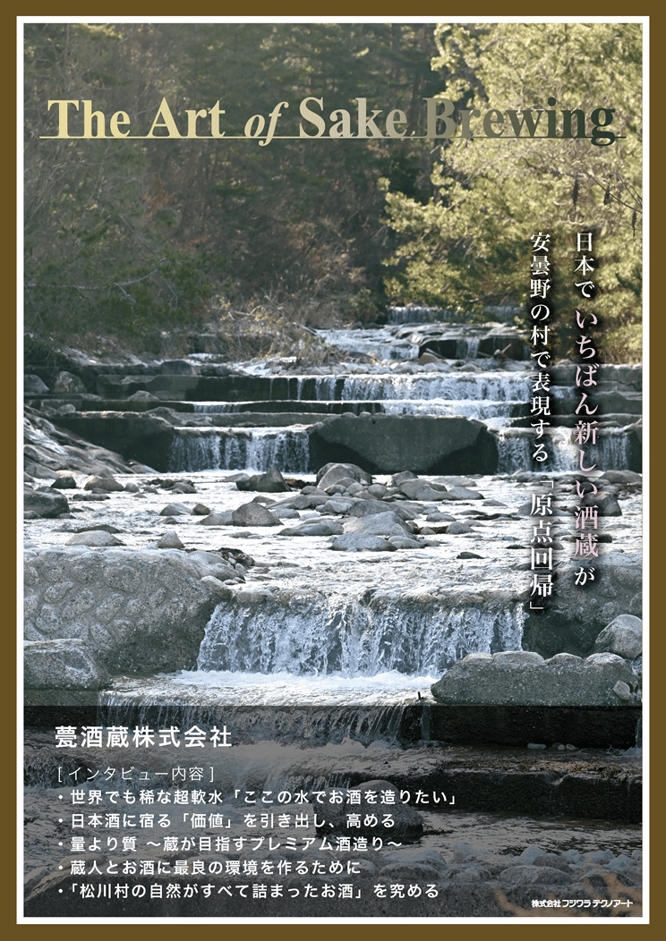
日本でいちばん新しい酒蔵が安曇野の村で表現する「原点回帰」
甍酒蔵株式会社 専務取締役 田中 勝巳 氏
[インタビュー内容]
2024年11月、長野県松川村に“日本でいちばん新しい日本酒蔵”、甍(いらか)酒蔵が誕生した。松川村の水と風土に惚れ込んだ杜氏・田中勝巳氏と甍酒蔵の仲間たちが、「松川村の自然をすべて詰め込んだ」究極の酒造りに向けた一歩を踏み出した。

甍酒蔵株式会社 専務取締役 田中 勝巳 氏
世界でも稀な超軟水「ここの水でお酒を造りたい」
甍酒蔵の蔵が建つ松川村は、北アルプスの麓に位置する自然豊かな村だ。この場所を選んだ背景には、醸造責任者(杜氏)である田中勝巳氏の「日本酒造りの原点回帰」への思いがある。田中氏が思い描く「原点」とは、その土地の水、そして周囲の田んぼで採れた米を使って日本酒が醸されていた昔ながらの酒蔵の姿だ。

甍酒蔵が事業承継した1665年創業の歴史ある酒蔵も、かつては田園風景に囲まれていた。しかし、時代が進むにつれ、周囲の田んぼは宅地に変わり、酒造りに適した良質な水も失われてしまっていた。前身の酒蔵の建物を活かしたい思いはありながらも、酒造りの生命線とも言うべき水に妥協は許されない。田中氏は、新天地を求めて「水が良い場所」を訪ね歩いた。

「井戸屋さんに良い水が出る場所を相談したところ、地図上に赤マルで示された場所が松川村でした」と、田中氏。「松川村の水は、世界でも稀な超軟水です。ここの水を初めて口にした瞬間、この水でお酒を造りたいと確信しました」
松川村は、水以外にも日本酒造りに理想的な条件を備えている。まず、乾燥した気候は病害虫の発生を抑え、農薬を最小限に抑えた米作りを可能にする。現に、松川村は長野県の酒米生産の一大拠点となっている。さらに、田中氏は「『村』は日本の自治体の最小単位です。昔ながらの風景が残る松川村は、まさに日本酒造りの原点回帰にふさわしい場所だと考えました。この土地の水と周囲の田んぼで育てられた米を使って、酒を造る。これこそが、甍酒蔵で実現したい酒蔵の在り方でした」という。

蔵の名前「甍」にも、土地とのつながりが込められている。「甍」という言葉には「屋根の最上部」という意味がある。松川村の背後にそびえる山々は、「日本の屋根」とも呼ばれる北アルプス連峰だ。雄大な自然の屋根を背にした酒蔵のありようを、「甍」の一文字が体現している。
日本酒に宿る「価値」を引き出し、高める
こうして生まれた甍酒蔵で、田中氏は「日本酒の価値を創造したい」と話す。「日本酒は日本の伝統文化です。しかし、時代の流れの中でその価値が薄れてしまいました。日本酒の価格は、昭和の時代からほとんど変わっていません。世界の醸造酒と比べても原材料費が高いにもかかわらず、最も安い醸造酒となってしまっている。この現状をどうにか打破したいのです」。

日本酒の価格が上がりにくい要因のひとつとして、田中氏は「等級制度の名残」を挙げる。「旧酒税法時代には、一級、二級、特級という級別で日本酒が分類され、その価格が横並びでした。それが特定名称酒に移行した今も、純米酒や吟醸酒、大吟醸酒といった名称ごとに価格が並ぶ状況は変わっていません」。
こうした状況を打破すべく、甍酒蔵では精米歩合を非公開としている。田中氏は、「『これだけ米を磨いているからこの価格』という思考から抜け出し、『この土地で、この水と米、そして風土から生まれたお酒だからこそ価値がある』。そんな新しい価値基準を提案したい」と話す。
甍酒蔵が醸造開始して間もなく、地元住民を対象に「村限定酒」を発売した。720ml(4合)瓶で税込2200円と、比較的高価格帯の設定だったが、当初仕込んだタンク1本分がわずか2カ月で完売。「村で売れるだろうか」との懸念は杞憂だった。田中氏は、「甍の4合瓶が村の食卓に並ぶ景色を見て、日本酒の未来を垣間見たように感じました」と語る。
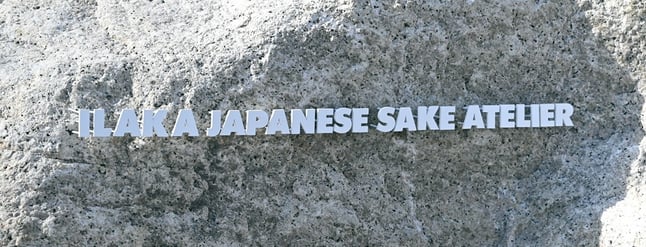
価値創造のフィールドには、国内だけでなく海外市場も含まれる。グローバル展開を見据えた社名には、「ILAKA JAPANESE SAKE ATELIER」という名称を使用。なぜ「ブルワリー」ではなく「アトリエ」なのか。その理由について田中氏はこう説明する。「海外では『ブルワリー』という言葉はビール醸造所を指します。日本酒をクラフトマンシップにあふれる特別な存在として伝えるには、『アトリエ』がぴったりだと考えました」。
現在、香港や韓国といったアジア市場を皮切りに、世界へと展開する準備を進めている。「ただし、どこに出すか、誰と組むかが重要です。市場に出せば売れるというわけではなく、日本酒の価値を正しく理解し、伝えてくれるパートナーが不可欠です」と、田中氏。日本酒の価値を創造し、地元から世界まで発信する甍酒蔵の挑戦は、まだ始まったばかりだ。
量より質 ~蔵が目指すプレミアム酒造り~

甍酒蔵の酒造りにおいて特筆すべきは、「量より質」を徹底的に追求する姿勢だ。すべての仕込みタンクに、出品酒を仕込めるクオリティの小規模タンクを採用し、年間生産量を増やすことよりも1本1本丁寧に仕込むことを優先している。

商品ラインアップは、それぞれ特徴が異なる銀黒、銀紅、銀藍の3タイプに分けられる。黒は「甍酒蔵が打ち出す王道の味わい」、紅は「甘い香りから意外な辛口に切れる味わい」、藍は「香りにドライな印象を持たせつつ、旨味の残るタイプ」となっている。いずれも個性豊かでギャップを楽しめるお酒でありながら、バランスの良さが共存しており、飲み飽きない。
3タイプそれぞれにディフュージョンラインの「銀」とプレミアムラインの「金」、「白金」があり、プレミアムラインの原料米には完全無農薬の酒米を使用している。プレミアムラインの酒質は「シルクのような舌触り」と田中氏が表現する通り、滑らかで繊細な味わいを堪能できる。「金」はより味のバラエティが楽しめる賑やかさ、「白金」は上品で洗練された味わいを備えている。

従来、日本酒は酒質の安定感や再現性を重視されがちだ。しかし、甍酒蔵では、仕込みごとに生まれる違いが日本酒の面白さや価値をもたらすものと捉えている。「同じご両親から生まれてきた兄弟でも、性格や立ち振る舞いが違うでしょう」と、田中氏。甍酒蔵の酒もまた、仕込みタンクごとに少しずつ異なるニュアンスを持つ。田中氏は、「芯がぶれていなければ、味の違いもむしろ面白い。お客様が『これは何が違うんだろう? 仕込みかな?』と考えるような楽しみを提供したいのです」と、笑顔を見せる。
量を追わず、質にこだわり抜いて生まれた1本1本は、単なる酒精飲料「製品」としての枠を超え、「ILAKA SAKE ATELIER」の「作品」としての存在感を放っている。
蔵人とお酒に最良の環境を作るために
甍酒蔵の酒瓶のラベルには、杜氏だけでなく蔵人の名前も記されている。そこには、「酒造りは一人では成し得ない。仲間がいて初めて成り立つ」という田中氏の信念が込められている。
田中氏は、杜氏の役割についてこう語る。「杜氏の仕事というのは、全体像を想像し、計画を立て、そして何より『環境を整える』ことだと思っています。蔵人たちが働きやすい環境を作ること、気持ちを奮い立たせるような雰囲気を作ることが、良い酒を造るために不可欠です。そしてもちろん、お酒そのものにとっての環境作りも。『今、どんな気持ちで発酵しているんだろう?』なんて想像しながら、最良の環境を整えてあげる。それが杜氏としての私の務めです」。

フジワラテクノアートは、そんな田中氏の思いを形にすべく、甍酒蔵の環境作りに伴走した。
田中氏とフジワラテクノアートの出会いは、田中氏が長野県の蔵元で専務兼醸造統括責任者を務めていた頃にさかのぼる。その蔵元の設備を手がけることとなったフジワラテクノアートの技術営業担当は、まだ入社間もない高岸だった。
田中氏は当時を振り返り、「あの頃の高岸さんは全部が中途半端で、よく叱っていましたよ」と笑う。
しかし「今や、高岸さんなしではこの蔵は建たなかったと言えるほど、頼りになる存在です」と、高く評価する。
高岸も、「自分で思い返しても未熟でしたね。田中専務には、仕事のやり方をイチから教えていただいて……」と述懐する。「あのときのご恩をお返ししたくて、今回、甍酒蔵の立ち上げのために自分にできることは何でもやろうという覚悟で臨みました」。

甍酒蔵の設備で田中氏が最初に導入を決めたのが、フジワラテクノアート製の「甑(こしき)」だった。原料処理工程、なかでも「蒸し」工程を重視する田中氏にとって、甑は、蒸し米の仕上がりを左右する重要な設備だ。
「フジワラテクノアートの甑で蒸した米の蒸しあがりを見たときに、これがいいと確信しました。営業の押しも相当強かったですが(笑)」(田中氏)。

容量は敢えて大きめの1ton用を導入し、米の量を最大容量の4割に限定して蒸すという贅沢な使い方を実践している。「広く薄く米を盛ることで、蒸気が1粒1粒にムラなく行きわたります。その結果、均一に米が蒸しあがり、さばけの良い蒸し米ができます」と、田中氏。
蒸しあがった米は、クレーンで隣の冷却機へ移され、素早く冷却されて麹室や酒母室へと運ばれる。この一連の作業は、杜氏と蔵人たちの熟練した連携プレーによって効率的に進められている。

そして、もう一つの重要な設備が、「計量洗米浸漬装置 Solo」だ。この洗米機は、高岸が田中氏の要望を受けて特別に開発を進めたものだ。
田中氏は、限定吸水の条件下で米を洗い、浸漬する作業工程は、「実は酒蔵のいちばんの見せ場のひとつです。その作業風景を目にしたお客様が『酒造りをしているな』と感じられる瞬間でもあります」と語る。このため、田中氏は無人運転が可能な回転式自動洗米浸漬装置の導入は選択肢に入れず、作業の様子を残しつつも省力化を実現したいと考えていた。
「高岸さんに相談してみたら、『やり方次第で、できます』と言うじゃないですか。とはいえ、バッチによって浸漬時間がまちまちなので難しいだろうと思っていました」(田中氏)
高岸は、田中氏からの相談を受け、社内のプログラム担当者の力を借りて開発に乗り出した。酒造りの現場を知る営業担当者として、米の投入時間を自動的に調節する機能、現在の作業と次の作業を把握しやすい画面表示やタイマー機能などが必須であることを痛感していた。一方で、作業が重複しないよう米の投入時間を自動調整する制御機能のプログラミングが容易ではないことも理解していた。「本当にここまでの機能が必要なのか?」「はい、絶対に必要です。お願いします。」「分かった。やってみるか。」プログラム担当者との間でそんなやりとりを重ねながら、複雑かつ精密な制御機能を持つシステムが完成した。
「しばらくして高岸さんが、『こんな機械装置ができました』と計量洗米浸漬装置 Soloを提案してくれました。まだどこの蔵にも入っていない機械だというので、『それなら甍酒造で1番最初に入れよう!』と導入を決めました」と、田中氏。「3~4人必要だった洗米・浸漬・脱水の工程を1人で完了できるのですから、かなりの省力化になります。機械本体のイニシャルコストも、人件費に換算すると数年でペイできてしまいます」。加えて田中氏は、計量洗米浸漬装置 Soloの洗浄力についても「洗浄力が高く、糠の残りが少ない」と高く評価。「これから日本全国の酒蔵で活躍する機械になるでしょう」と太鼓判を押す。

モニターに「次の作業」がタイマー表示され、これに従えば洗米浸漬が一人作業で完結する。

浸漬の様子。半自動洗米機によって糠が除去され、浸漬水が透き通っている。
「松川村の自然がすべて詰まったお酒」を究める
「日本酒の価値を創造する」という目標達成への道のりは、長く険しい。頂上までの進捗具合は「まだ、2合目を踏み出したくらいでしょうか」と、田中氏。「蔵の中だけでも、挑戦したいことが山ほどあります。甑にしてももっと良いふかし方があるだろうし、洗米機ももっと良い使い方ができるでしょう。蔵で生み出したものを世の中にご案内していくのは、その次の段階。本当にやりたいことを形にしていくのは、まだまだこれからです」と意気込む。

そんな田中氏に、甍酒蔵が目指す「究極の日本酒」を聞くと、「松川村の自然がすべて詰まったお酒を造りたい」との答えが返ってきた。「松川村の水は、世界でも稀な超軟水でありながら、その口当たりには独特の弾むような丸みがあります。この水を最大限に活かしたお酒を造りたい。ジューシーで、口の中に入れた瞬間に弾むようなお酒を造れたら、それを飲んだ方に幸せを感じてもらえるだろうと思います」。
機器カタログ
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。